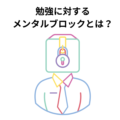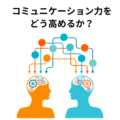こんにちは!今日は「学ぶ大人応援ラジオ」のエピソードから「計画は綿密にする?またはざっくり?」というテーマでお送りします。このエピソードでは、リスナーの方からの勉強計画についての悩みに答える形で、計画の立て方について深掘りしていきます。
相談内容
リスナーの方からこんな質問をいただきました。
「勉強計画は1日単位で細かく立てた方がいいでしょうか、それともざっくりと立てた方がいいでしょうか?以前、1日単位で綿密なスケジュールを立てたことがあるのですが、遅れが出始めるとどんどん気持ちが萎えてしまい、そのまま投げ出してしまったことがあります。ですが、ざっくりすぎると日々やることがわかりにくいという難点もあり、迷っています。」
綿密な計画とざっくりな計画、一体どちらが良いのでしょう?
ざっくり計画のアプローチ
ざっくり計画するアプローチは、マラソン大会の準備が一つの例になるかもしれません。
「○ヶ月後に42.195キロ走り切る」という長期的な目標から逆算して、まずは4分の1の距離を走れるようにし、次に半分の距離をクリアするという具合に、段階的な目標を大まかに設定します。
4分の1の距離であっても最初は大変なので、いつまでにクリアできるか見通しがつかない中でも挑戦を続け、自分の体力がつくとともに徐々に達成時期が見えてきます。達成時期が予測できてきたらざっくりと次のフェーズに入る時期を決める、というように、初めから細かくスケジュールを引くのではなく、進捗を見ながら随時最終目標に向けてスモールゴールの時期を考えていくという方法です。
こうすることで初めに決めてしまった無理のあるスケジュールが心理的負担になることなく、一歩一歩足元からゴールへの歩みを進めていくことができます。
綿密計画のアプローチ
一方、綿密な計画を支持するアプローチでは、仕事や学習の目標達成のために、デイリーや時間単位での詳細なスケジュールを立てる方法がイメージしやすいかもしれません。このアプローチは、達成すべき具体的なタスクを明確にし、計画通りに進むことで得られる達成感がモチベーションを高めることに繋がります。しかし、計画通りに進まなかった場合のストレスを軽減するため、適度なバッファーを設けることが推奨されます。
バランスを取るための方法
どちらのアプローチにもメリットとデメリットがあり、状況に応じて使い分けることが大切です。
長期目標と短期ステップの組み合わせ
長期的な目標をざっくりと設定しつつ、直近のステップを細かくリスト化する方法があります。例えば、次の3つのステップを常に目に見える形で管理し、それをこなしたら次のステップに進むという具合です。こうすることで、綿密さとざっくりさのバランスを取りながら進めることができます。
バッファーを設ける
綿密な計画を立てる際には、必ずバッファーを設けることが重要です。計画通りに行かないことがほとんどなので、余裕を持たせたスケジュールを組むことで精神的な負担を軽減し、計画の柔軟性を保つことができます。
リスケジュールの習慣化
計画が遅れた場合、定期的にリスケジュールを行うことも有効です。月に一度、計画を見直し、現状に合わせて調整することで、計画と実態のズレを最小限に抑えることができます。こうしたリスケジュールの習慣をルーティンにすることで、計画が現実的で実行可能なものになります。
まとめ
計画を立てる際には、自分の性格や状況に合わせて、綿密さとざっくりさを使い分けることが重要です。特に、ストレスを避けるためにはバッファーを設けることや、適宜リスケジュールすることが有効です。勉強や仕事の計画で悩んでいる方は、今回のアドバイスを参考に、自分に合った方法を見つけてください。
勉強継続コーチングのご案内
もし、自分一人での計画立てやリスケジュールが難しいと感じる方は、勉強継続コーチング StudyHabit を利用するのも一つの手です。オンラインでコーチと一緒に月に一度、計画を見直しながら進めることで、安心感を持ちながら目標に向かって進めることができます。
以上、今回は「計画は綿密にする?またはざっくり?」についてお話ししました。皆さんの参考になれば幸いです。